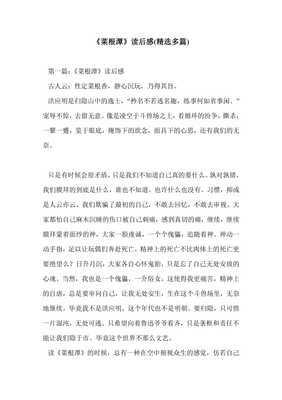
《欲望》是一本由小池真理子著作,译林出版社出版的369图书,本书定价:18.40元,页数:2004-1,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。
《欲望》精选点评:
●很多年前读的,大学时偶然买到国内出的原文版,只记得一种窒息一般的美学,的确有点三岛味道。
●在文摘中读到第一段,即被吸引,欲言又止,意味悠长,原本以为只是一小段的随笔,没想到却是数百页的长篇,符合小池真理子中年妇女的形象——闷骚。
●经典到已经不想什么了
●最大印象是语言优美~~~~~ 同样一句话 小池写出来就让人小心脏直颤颤
●好看
●将肉体的欲望和精神的欲望融合得酣畅淋漓,本书值得一读!
●终于读完了。 好复杂的人物及情感关系。 比某人翻译的那部要复杂几万倍吧。
●蛮好看的,我对心理描写好的作家欲罢不能
●见书评
●促使我想看三岛由纪夫的书
《欲望》读后感(一):夜读笔记
冷雨敲窗不可听,
挑灯闲看牡丹亭。
人间亦有痴如我,
岂独伤心是小青。
====================================
昨晚不晓得梦到什么,只记得我一直在梦里摇头,因为摇得太厉害,把床头堆的书摇倒了。砸在脸上的正是睡前读的《欲望》。醒来之后睡不着,于是就打开台灯趴在床上接着读了起来。不知不觉就读到天明····
日本的恋爱小说里多有人死亡,大概是因为爱的太惨烈了吧。作为纯粹的美而存在的阿佐绪死掉了,能写那么深情的信的正己也死掉了,连那个只在图书馆里读三岛的女生也死掉了,离去的都是美丽的人。留下了衰老的恗田和身为人妇的类子,凝望着如空空如也的夏日庭院,读着三岛的《天人五衰》,回望着二十年前梦一场。
小池的书是第一次读,一开始觉得颇像江国香织,但细读又不一样。直男肯定会喜欢这本书,想推荐给他看,可惜目前还没中文版。真不晓得有谁能将这样的文字翻译出来。
对了,正己用邮票做的那个夜间勃起试验,我初中时也做过,呵呵,看到这段的时候亲切极了··
另外,书中还有一个细节。正己出车祸时,阿佐绪给类子打电话,背景播放的音乐是当时的流行歌曲《戀の季節》,这首我也很喜欢
忘れられないの あの人が好きよ
青いシャツ着てさ 海を見てたわ
私ははだしで 小さな貝の舟
浮かべて泣いたの わけもないのに
恋は 私の恋は 空を染めて燃えたよ
死ぬまで私を ひとりにしないと
あの人が言った 恋の季節よ
恋は 私の恋は 空を染めて燃えたよ
夜明けのコーヒー ふたりで飲もうと
あの人が言った 恋の季節よ
恋は 私の恋は 空を染めて燃えたよ
夜明けのコーヒー ふたりで飲もうと
あの人が言った 恋の季節よ
恋の季節よ 恋の季節よ
《欲望》读后感(二):《欲望》:刻写的姿态
娉婷初现,琵琶湖畔枕经眠。人性的呜咽,未尝不具有沦陷的象征。
读书期间普普通通的女生类子与美貌无暇的阿佐绪、英俊的正已是最交好的同学。类子暗恋正已,正已却爱着生性懒散——白壁无缺、却有璀璨夺目的阿佐绪。星移物换,正已遭遇车祸,失去了性功能;阿佐绪嫁给了顺势尊崇三岛由纪夫美学的袴田,却没法获得真爱;类子成为学校图书管理员,和校员开始了一段始于且终于肉体的爱恋,也成为阿佐绪和正已二人不幸的观众。
三岛的浓烈可怕到窒息,具体而立体的人物群像,细致敏锐的心理分析,心心念念的人物心智,都将青葱赋予一旦,类子作为读心术的密缕细针,以魔力胭脂一般的心性席裹了暗和怕,力和命作为旨归被强调,爱火被高烧,心中尤凄艳。
阿佐绪的懒散性格固然有其不美好,她除了会钢琴之外什么也做不成功,只有她的天生一段风流美貌,她并没有所谓的权力意志,不懂得如何去操控别人——操控爱人,但是类子从来就是把她当成一个闺蜜知己来看待,并没有因为正已对阿佐绪的强烈思慕而有所嗔怪。因为阿佐绪的真情真性。
在青葱岁月中试图和类子发生关系的正已,陡然发现了那个不堪的秘密,然而却燃烧了他们之间的爱火,二人希图的是永久的陪伴。类子和校员能势之间的性关系,不过是汗水的浇筑与雕刻,而类子和正已之间的零关系,却是更为深刻且久远的陪伴。
千山暮雪,只影向谁去?阿佐绪认为世事艰难,袴田和佣人水野的妻子有了孩子之后,和水野的妻子开车同归于尽。此时的阿佐绪,约莫是真正的自己,既成全了意志,又通过报复刻写了某种姿态,以此回复一种权势对于她的轻视。
在类子向能势坦承自己喜欢上别人之后,她决定彻底结束和能势的关系,又与正已旅游期间,虽未行事两人极尽风流骚动。因为类子与正已之间的关系,除了深刻的卿卿我我曲曲弯弯之外,更是粘腻的精神主义象征。诚如书中所写,即使是想象中的肉体,对他们而言,都是处于现实延长线上的东西。情欲勃发,亦是精神所求。在阿佐绪死后,类子和正已去海边度假时分,正已故意在海上游泳时自尽。
为何他要自尽?面对恋情的率性纯真,与抛弃了知性与理性的傲慢坦承。正已之所以拥有类子还要自尽,也许是还是无法面对十六岁时的车祸酿成的后果吧。俗气的哀叹只能是敌人。年少时光,月下阑珊清扬俱是风流意,他如果可以从内心的怆痛走出来多好。那个带点狂放气质的年轻人,自尽说明他内心的孱弱。或许还不如阿佐绪,因为阿佐绪最终以自己的意志成全自己。
良辰美景奈何天,赏心乐事谁家院?
《欲望》读后感(三):《欲望》读后感—三岛由纪夫《丰饶之海》的绝妙互文
读书获得知识,或感到愉悦,或打发时间,都算收获。不知道书的背景没什么,就像不知道读的是《红楼梦》哪个版本一样,不影响我们用自己的眼光欣赏。那些红学家脱离了文学的“考据”研究,对普通人来说实在无用。不过这次读的《欲望》,我恰巧有一些小发现,也有点“考据”意味。但这本书如今只有日文版,中国的读者范围就很窄了,并且还要读过我的“发现”中的三岛由纪夫的多部作品的读者,就更加少了。所以我这文章虽涉及剧透,却无大碍,因为明白的人很少,明白的人只能都看过。
“互文”,本是古诗文中常采用的一种修辞方法,不过现在也用于把某部甚至某些原创作品里的人物或人物性格的化身放在新环境里,加入作者自己的想法,表达新的主题。通俗的讲实际上就是“同人文”。不过“同人文”多指对动漫作品,“互文”则多指对著名文学家及其作品的再创作。当代爱玩儿互文的有诺贝尔奖获得者库切,如他的《彼得堡的大师》与陀思妥耶夫斯基,诺贝尔获奖演讲和《福》与迪福的《鲁滨孙飘流记》。库切的互文比较明显,虽然部分内容有些晦涩难懂,但是一眼就能看出“互”的对象。小池真理子的这本《欲望》就不一样了,她打着通俗爱情小说的幌子,具有一切爱情悲剧小说的要素,三岛由纪夫貌似只是其中的线索,可是我读过两遍后,坚定地认为《欲望》是三岛《丰饶之海》的不折不扣的互文。
从情节上来说,外表美丽的阿佐绪和正巳相继死去,可以看作对《丰饶之海》中各主角的死的模仿。作为美丽的化身们,死是他们的完美归宿。这也是三岛追求的最终境界,得过健美冠军的三岛本人,最后剖腹自杀。外表美丽,精神纯粹,死。
而最后一个场面,类子去找袴田的描写,是对《天人五衰》也是整个《丰饶之海》最后一个场面的模仿。几乎每一个细节都在模仿,初时觉得很牵强。后来才明白这不是作者的模仿,而是塑造的人物性格决定的,女主人公和垂老的袴田本身在模仿那个场面。
读第一遍时,总感觉主人公类子的性格有些别扭,比如男主角正巳和她在海边缠绵了一周后,淹死了,她说自己没哭过,没绝望。比如与离不开的性伙伴能勢吵架后,能勢夺门而出,她说自己不悲伤,不愤怒,不惊讶。等等心理描写随处可见(具体见后附),与当时情节给人的印象极为不符,如果说这是作者营造出来的主人公性格,这性格也未免太做作。
但理解了本小说的互文性质后,我觉得这种别扭的性格,正是合理的。三岛笔下的意象、心理状态甚至情景都会重复使用。例如《丰饶之海》四部曲中的四个转世主人公(最后一个是假的)。而《欲望》中,两个男人对三岛意向的模仿是明笔,在书中他们都明确表示对三岛的喜爱。袴田更多的是对三岛本人的模仿,虽然他自己说三岛只不过是像他。秋葉正巳则是三岛笔下常见人物的化身,如月光姬(《晓寺》)、安永透(《天人五衰》)。正巳美丽的身体,缺陷的美丽,纠结的精神,都如他们一般。
两个女人是暗笔。阿佐绪纯粹的外在美丽,钻牛角尖的激烈性格让人想到了饭沼勋(《奔马》)。最后疯狂地同时也是基于自身意志的自杀就是一个例证。另一个女人就是主人公,作为叙述者“我”的青田类子。这才是互文的《欲望》隐藏最深的角色,也是最成功的形象塑造。类子的经历有着《丰饶之海》贯穿四部的本多繁邦的影子,又有最后遁入空门的绫仓聪子的抹去记忆的能力,又有松枝清显(《春雪》)的深爱却故意矜持的矛盾性格……但是又都无法定论。从《欲望》中,我们知道类子是因为喜欢正巳,而正巳喜欢读三岛的书,类子爱屋及乌,也喜欢上了三岛的书,在模仿中,改变部分自己,形成矛盾的性格,却还保留了理智。这才是作者互文的真正目的,并非按照三岛的行文结构换上几个人物重新编排,而是在探讨作为三岛的忠实读者,受到三岛影响,并经历类似三岛书中的人生经历后,有怎样的矛盾表现。作者本人能写出这种互文,说明对三岛的深刻研究和推崇。也许,类子就是作者自己的代言人。
附主人公类子的别扭心理:
从偶然认识的人那儿,突然听到正巳的名字,但我得心情却没有一点儿起伏。
(能势夺门而出)没有悲伤。没有愤怒。没有惊讶和不安。
(相见正巳)想见他,想看他的脸,想听他的声音,想和他说话。我祈求着。但祈求的只是这些而已。即使使用假定法,假定正巳的性能力恢复了,我也不会想着他的身体。发誓也可以,我决不会想!
(等正巳的电话)对总也不来电话这事儿,我一点也不生气。为什么不来电话呢,这个那个胡思乱想,刨根问底的事情也没有过。…即使让我等半年,我也可以没有任何怀疑和不安。
(正巳死后)小说或电影中那种常见的哭天喊地,绝望发狂,自己也去死吧,这样强烈的感情我一样也没产生。
《欲望》读后感(四):『欲望』書評―三島由紀夫の魂が漂っている
「互文」、元は漢詩において常に採用された修辞の方法である。今、ある著作ないし複数の作品の人物あるいは人物の性格の化身を新しい環境の中に置き、作者自身の考えを加えて、新しい主題を表すことにも用いられている。分かりやすく言えば、「同人文」とほぼ同じようである。ただ、違うのは、「同人文」は主にアニメ?漫画の作品の二次創作を指しているが、「互文」の多くは有名な文学者と作品の再創作を指している。現代、「互文」を使いこなしているのは、ノーベル賞の受賞者のクッツェーである。『ペテルブルグの文豪』とドストエフスキー、ノーベル賞受賞の講演および『敵あるいはフォー』と『ロビンソン?クルーソー』。小難しい内容もあるが、クッツェーの「互文」の対象ははっきりして、一目で分かる。それに対して、小池真理子のこの『欲望』が通俗恋愛小説を表看板にして、恋愛悲劇のすべての要素は揃っている。三島由紀夫がこの小説の飾り物だと思ったのに、二回読んでから、『欲望』は三島の『豊饒の海』の徹底的な「互文」だと確信している。
筋によれば、外見の美しい阿佐緒と正巳が次々と死んでしまったことは、『豊饒の海』の各主人公の死の模倣と見なされる。美の権化たちとして、死は完璧な帰着である。これも三島は追い求めていた最終の域。ボディービルの優勝を得たことのある彼は、結局、切腹自殺した。外見の美、純粋な精神、死。
類子と袴田についての最後のシーンの描写が『天人五衰』および『豊饒の海』の最後のシーンのまねをする。模倣はあちこちにあるので、こじつけだと思った。今、それは作者の模倣ではない、作った人物の性格によって、主人公類子と老衰の袴田自身はそのシーンのまねをしていたとようやく分かった。
はじめて読んだとき、主人公の類子の性格が変っているように思えてならなかった。たとえば、海辺でロマンチックな一週間を過ごして、正巳が溺死した時、彼女は「泣き喚くとか、絶望のあまり気がふれるとか、……一切、生まれなかった」と独白した。また、離れられないセックスフレンドの能勢が彼女とけんかして、飛び出した時、彼女は「悲しくはなかった。怒りも生まれてこなかった。驚きも不安も何もなかった。」と独り言を言った。このような心理の描写がどこにも見られる(詳細は最後に付け加える)が、当時の文脈から読者にあげる印象ととても一致していない。作者がわざわざ創った主人公の性格と言っても、この性格はあまりにわざとらしすぎるようである。
ところが、この小説の「互文」の本質を理解してはじめて、主人公の変な性格こそ、合理的極まりないと思うようになった。三島の著作の中のイメージ、心理状態、シーンまで繰り返す。『豊饒の海』4部シリーズの中の輪廻転生の4個の主人公(最後の一人は偽者だが)がいい例である。『欲望』の中で、三島のイメージのまねをする二人の男の人ははっきりしている。二人とも三島を好むのを隠さない。袴田は多く三島本人のまねをする。彼は三島たまたま彼に似ているだけと言ったけれども。秋葉正巳のほうは三島の作品のよくある人物の化身で、たとえば、『暁の寺』の月光姫、『天人五衰』の安永透。正巳の輝いた体、欠陥のある美しさ、絡み合った精神、すべて彼らと同じである。
二人の女の人に対する「互文」描写は難解である。阿佐緒の純粋な外見の美と、盲目的で激しく思いつめる性格は『奔馬』の飯沼勲を思い付かせる。最後の気が狂いながら意志に基づいた自殺もその例証である。一方、話者としての主人公の類子はもっと難解で、「互文」の『欲望』の精髄である。彼女の経歴からみて、『豊饒の海』の四部を貫いた本多繁邦の影があるような気がするが、空門に入った綾倉聡子の記憶を抹殺する能力も備わっている、さらに松枝清顕(『春の雪』)のような熱愛しながら矜持する矛盾した性格も持っている…しかしどちらも定めではない。『欲望』によると、類子は正巳のことが好きだから、正巳の好物の三島の本が好きになった。そのまねをし、自分を変えて、変な性格になったが、理性を失わない。これは作者の「互文」の本当の目的かもしれない。つまり、三島の作品の作風と人物による二次創作ではなく、三島の忠実な読者として、三島の影響を受けて、三島の作品の典型的な人物ような人生を経てから、どうなるかと検討しているかもしれない。『欲望』のような「互文」を書けたのは、小池真理子さんが三島に対する深刻な研究と敬重が分かる。類子は彼女の化身かもしれない。
付録 類子の変な心理描写:
思いがけず、ひょんなところで知り合った人間から正巳の名を出されたわけだが、私の気持ちはつゆほども波立つことはなかった。
(能勢が飛び出した)悲しくはなかった。怒りも生まれてこなかった。驚きも不安も何もなかった。
会いたい、あって彼の顔が見たい、彼の声が聞きたい、話がしたい、と願う。だが、願うのはそれだけだった。もしも正巳に性の力が甦ったとしたら、という仮定法を使って、私が彼を思うことはなかった。誓ってもいい。そう思うことは決してなかった。
(正巳の電話を待つ)なかなか電話がかかってこないことに対して、苛立つ気持ちはまるでなかった。電話がかかってこないことの理由をあれこれ考え、詮索することもなかった。…私は半年の間、何の疑念も不安も抱かずに待つことができただろう。
(正巳が死んでいる)泣き喚くとか、絶望のあまり気がふれるとか、自分も死んでしまいたくなる、といったような、小説や映画の中でよく見られるような烈しい感情は私の中には一切、生まれなかった。